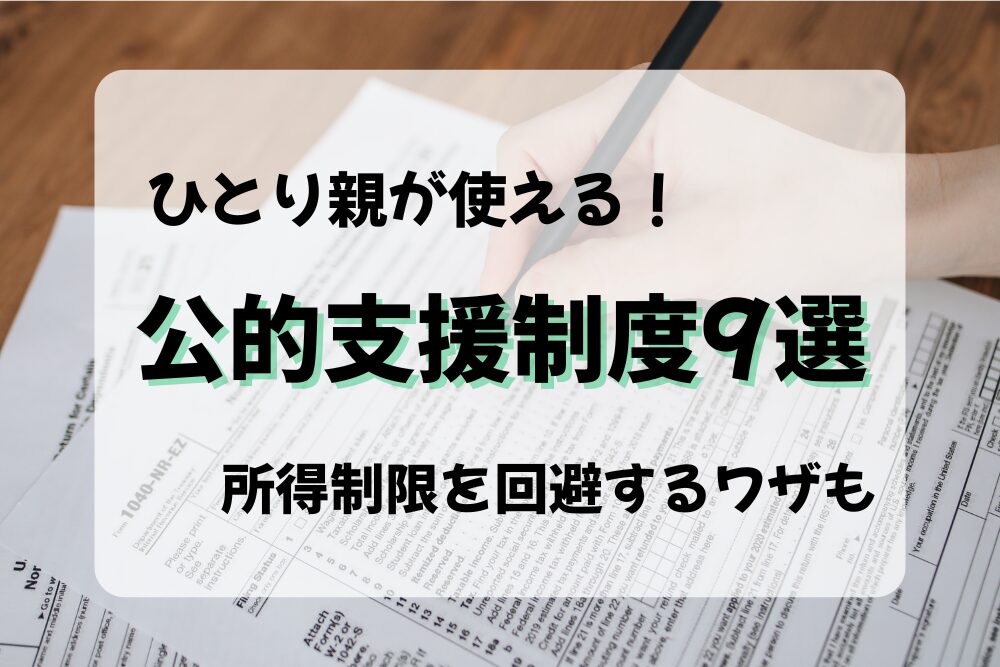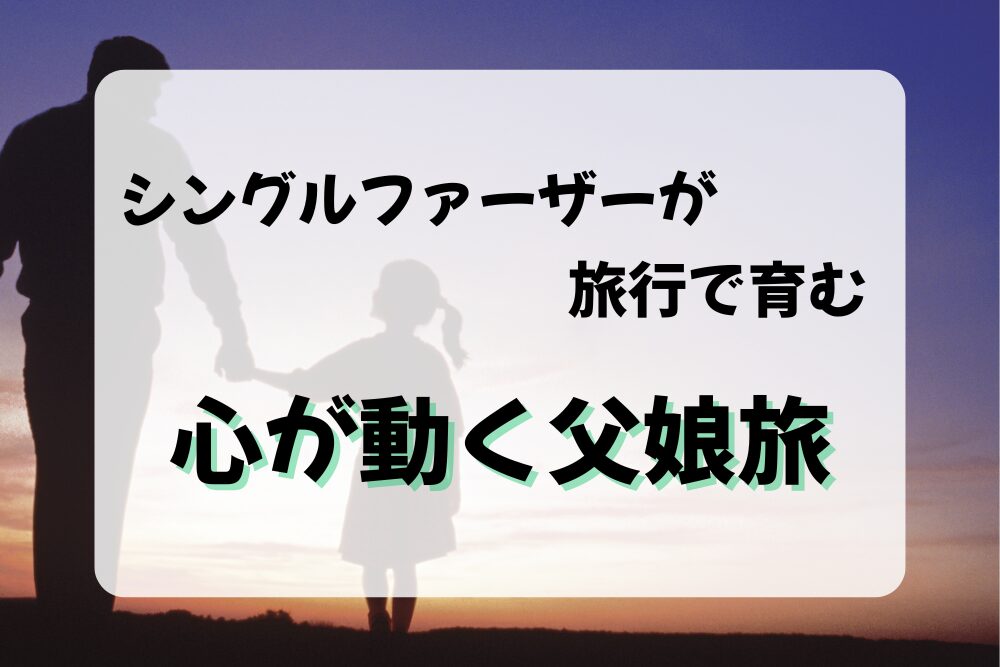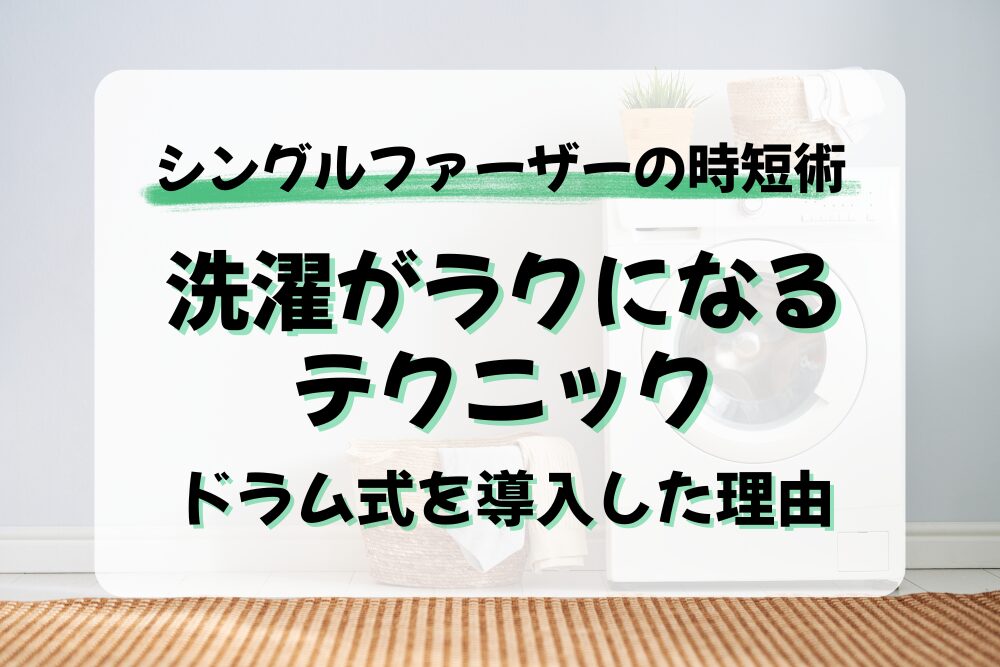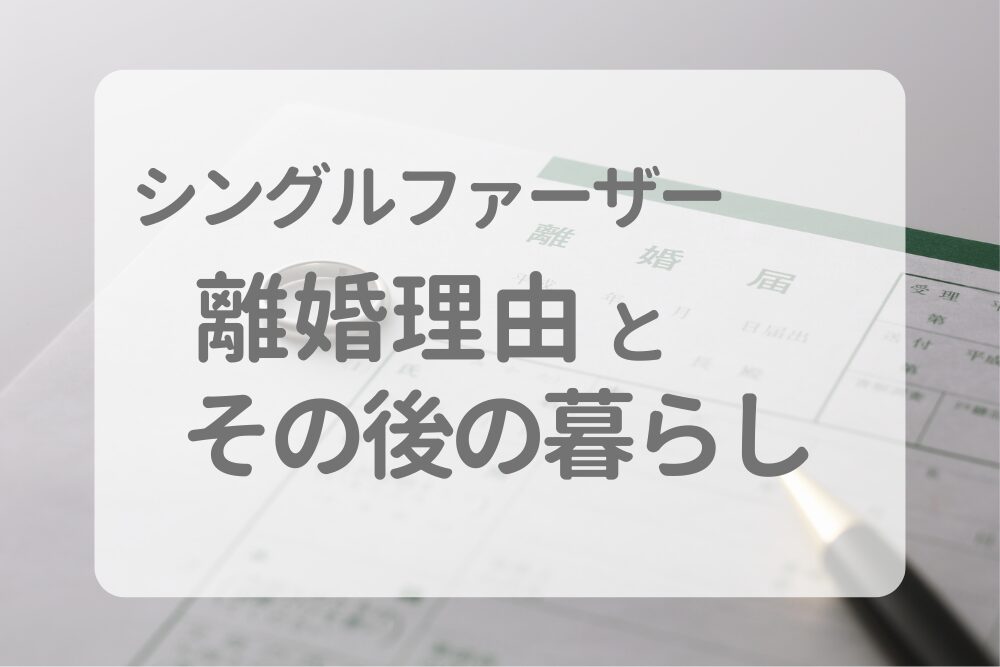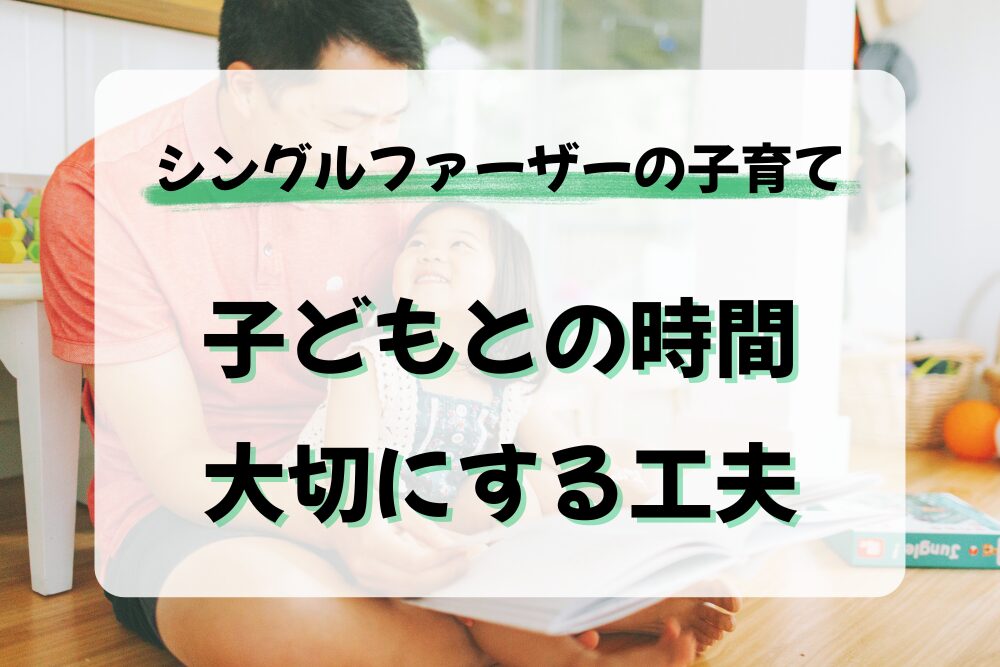離婚後の不安を力に変える!自己肯定感を育むシングルファーザーの子育て
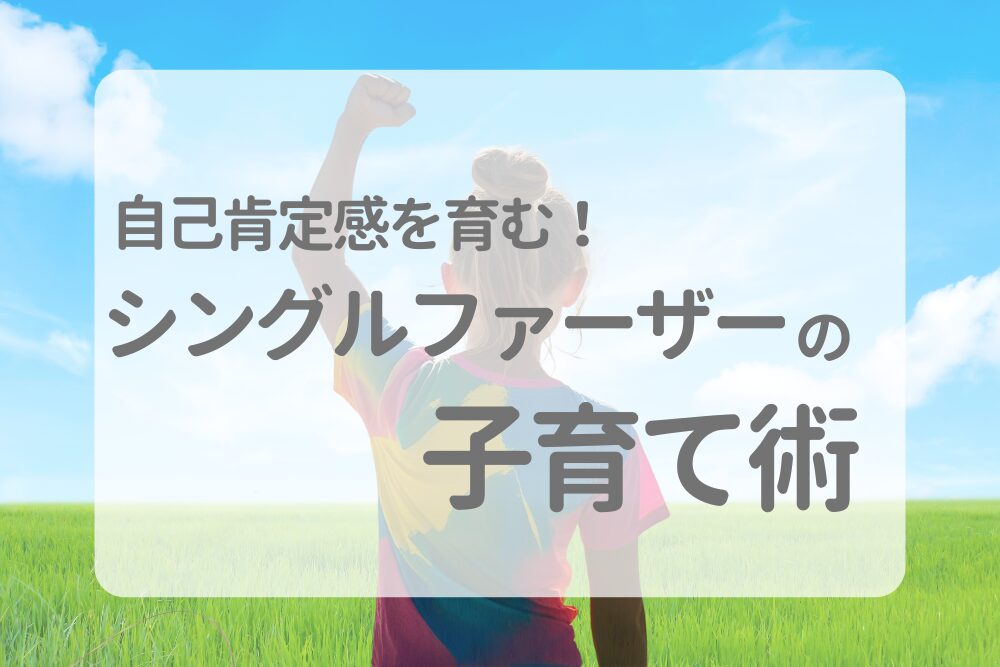
先日公園や商業施設などを娘と歩いていると、パパとママがいて楽しそうに歩いている家族を寂しそうに見つめる娘の姿がありました。

『私はこの子に寂しい思いをさせてはいないだろうか』

『母親と同じよう(母親がいる家庭と同じよう)に子育てできているだろうか』
と胸が苦しくなる時があります。
離婚したばかりで、このような同じ思いを抱いている方もいると思います。
この記事では、離婚によって不安を感じる娘に対して、どう考えてどう行動しているのか詳しくお伝えします。
離婚後の不安な中、子育てされている方の背中を押せれば幸いです。
そもそもどうして別れてしまったの?
私の離婚原因を一言で表すなら『価値観の相違』です。
経済的な行き違いや身近な人の不幸が重なり、お互いを思いやる余裕を失った結果、別々の道を選びました。
その過程でお互いしっかり話し合えていれば、おそらく別れることはなかったのではないかと思います。
当時、娘が板挟みにならないよう十分配慮したつもりですが、彼女がどう受け止めたかは分かりません。
現在の暮らしと親子コミュニケーション

娘と二人で暮らす日々は、仕事・家事・子育てが同時進行する慌ただしさの連続です。
それでも「母との時間」「家での安心感」「食卓での対話」という三つの柱を意識し、互いの気持ちを行き来させる仕組みを整えてきました。
私たちが離婚後に築いた暮らし方と、親子のコミュニケーションを保つ具体的な工夫を紹介しましょう。
月に数回の母娘タイム
離婚後も母子関係を絶やさないよう、娘は月に2〜3回、母親と買い物や食事に出かけています。
短い時間でも「母と娘だけの思い出」を積み重ねて、娘が双方の愛情を感じられるよう意識しています。
日常の暮らし
娘は父親の私と二人暮らしです。
私は自営業でほぼ終日自宅にいるので、炊事・洗濯・掃除などの家事は私が担います。
「時間」と「柔軟性」を両立するために、私は在宅ワークを選びました。
仕事の合間に家事タスクを細切れでこなし、娘の帰宅時には手を止めて迎える余裕を持つよう工夫しています。
私の働き方については、下記の記事で詳しく紹介していますので、参考にしてください。
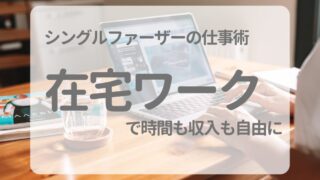
夕食は一緒に囲みコミュニケーション
夜ごはんは必ず同じテーブルを囲み、学校での出来事や友人関係について娘が話したいことを自由に語れる場にしています。
女性特有の悩みや友人との行き違いなど、私には共感や理解が難しいテーマもありますが、「まずは聞く」ことを最優先とし、安易なアドバイスは控えることを意識。
安心して話せる時間を作り、娘は自分のペースで感情を整理することによって、自己肯定感を育てられるのではないかと考えています。
『全米トップ校が教える 自己肯定感の育て方』で学んだこと
夕食の対話で娘の話を「ただ聴く」ことは意識できるようになったものの、「この声かけで本当に自信につながっているのか?」「失敗したとき、どこまで励まし、どこから見守るべきか?」迷う場面は尽きません。
そんな折、書店で目に留まったのが一冊の本でした。
『全米トップ校が教える 自己肯定感の育て方』(朝日新書)
この本が教えてくれた最大のポイントは、「子どもが自分を肯定できる環境をつくることが、親にできる最良のサポート」というシンプルな事実でした。

子供の自己肯定感を高めるために
- 小さなことでも褒める
- 成功体験を味わわせる
子どもが関心を持っていることで、新しいことに挑戦するよう促す - 失敗しても前向きな言葉をかける
失敗した時も、「また頑張ってみよう」「うまくできなかったけど頑張ったね」など、前向きな言葉をかける - 子どもの話を聞く
子どもが話したい時に真剣に向き合い安心感を与える - 選択する機会を与える
服や遊ぶおもちゃの選択など、日常生活で子どもに選択権を与える。 - 自然や文化に触れる機会を作る
キャンプや美術館訪問など、自然や文化に触れる機会を多く作る - スキンシップを大切にする
全部できないとしても日常で少しずつ取り入れていければ、娘の自己肯定感は高まってくるのではないかと考えています。
自己肯定感の成長を意識!わが家の実践例

自己肯定感を高めるコツを本で学んだら、即実践です!
我が家では山登りやテニスを通じて、次のようなことを意識しています。
- 小さなことでも褒める
- 成功体験を味わう
- 失敗しても前向きな声をかける
- 自然や文化に触れ合う機会を作る
具体的なエピソードを詳しく紹介します。
旅行先での山登り
これまでに私と娘は、「旭岳」や「燕岳」などの登山に挑戦してきました。
旭岳では急な天候変化に遭遇し、怖さを感じることもありました。
しかし一歩一歩着実に進み、目的地へ近づくたびに「ここまで来られたね」と声を掛け合い、登頂した成功体験が大きな自信につながったと思います。
燕岳での計画不足による体力の限界という状況も、今ではいい思い出です。
失敗や苦い思い出も、振り返れば「乗り越えた証拠」。
山登りで得られるこれらのプロセスが、自己肯定感を育てる貴重な教材だと感じています。
山登りなど旅行先でのその他のエピソードは、下記の記事で紹介しています。
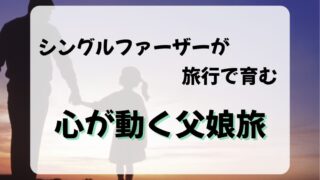
娘が主役のテニス
休日は娘とテニスを楽しむのが定番です。
プレー中は、ラリーが続くたびに「ナイスショット!」と褒め合います。
娘はテニスに対して意欲的で、「次はこうしてみる」と目標を立て試行錯誤を繰り返す姿が頼もしい。
このような過程が、自己肯定感を育んでいるのではないかと考え、私はサポーター役に徹し、挑戦する背中をそっと押し続けています。
限られた時間の中で、自己肯定感の成長を意識した関わり方の具体例を、下記の記事で紹介しているので、参考にしてください。
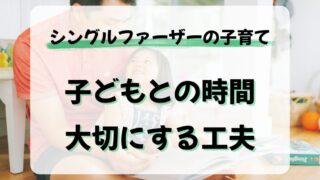
まとめ
シングルファーザーとして「母親がいない寂しさ」を完全に埋めることは難しいかもしれません。
しかし自己肯定感を育む関わりを意識し、子どもが「自分は大切にされている」と感じられる環境を整えると、親子双方が前向きに歩めます。
この記事が、不安を抱えながら子育てに向き合う同じ立場の方の背中を少しでも押せたら幸いです。